『ハンガー・ゲーム FINAL: レジスタンス』
The Hunger Games Mockingjay Part 1
6月5日から公開されてたなんて知らずに、
7月1日にあわてて駆け込み鑑賞。
大半の劇場で、本日3日で上映終了。
ここまでどうにか、見逃さずに来れたので、
後は11月20日に世界同時公開される最終作完結編
『ハンガー・ゲーム FINAL: レボリューション』
を見れば、ミッション完了となる。
オレは映画『ハンガー・ゲーム』シリーズに
ガッカリしたことは一度もない!
1作目
『ハンガー・ゲーム』(2012)


レビュー【その2】


売り上げランキング: 5,590
2作目
『ハンガー・ゲーム2』(2013)
売り上げランキング: 2,415
思うがままの独裁と圧政を続けるスノー首相(ドナルド・サザーランド)に対し、
ついに民衆が蜂起し、
叛乱が始まる。
そのリーダーにかつぎ上げられたのは、
偶然が重なって、「ハンガー・ゲーム」を生き延びた、
カットニス・エヴァディーン(ジェニファー・ローレンス)だった。
と言う本筋が、たっぷり時間を取って、
はしょらずに説得力をもって、じっくりと語られる。
(※以下、若干のネタバレ=赤字部分)
筋書きの都合もあって、
スノーが無敵の絶対悪にならず、
そこかしこにすきがあり、
また主要人物(正義側)は、
3本目の時点ではどうやら死なないと見透かせたのは、
ちょっといただけなかったが、
全体のバランスが破綻することもなく、
いたって満足。
(※ネタバレ終わり)
それより、1作目公開の2012年には絵空事だった
独裁支配国家が、
その年の年末から現実になってしまい、
それから丸々2年半が経過してるっていうのに、
渦中の国民が、この状況を予見していた「ハンガー・ゲーム」に、
まったく無関心っていうのが、
映画の内容より、よほどコワイよ!
今日中に見れば、まだ間に合うぞ!
『ハンガー・ゲーム FINAL: レジスタンス』(2014)
1/12スケールC-3PO/バンダイプラモ(10)
バンダイのSWプラモを、1アイテムずつ取り上げる連載の10回目。
売り上げランキング: 399
売り上げランキング: 1,221
売り上げランキング: 455
売り上げランキング: 286
売り上げランキング: 1,357
売り上げランキング: 1,773
前回がR2-D2だったから、
売り上げランキング: 300
今回は、その相棒の、
C-3PO
せっかく天下のディズニーに管理が移譲されながら、
12月公開の『フォースの覚醒』の公式表記でもまだ、
“See-Threepio”表記をローマ字読みだと勘違いして、
「シー・スリーピオ」なんて、
鎖国的カナあて
を続けるんだろうか…。
あのさあ、
“C-3PO”の英字綴りが
“See-Threepio”なんだから、
読み方が変わるわけないじゃん。
そもそも英米人が、
自国で使ってる言葉を、
ローマ字読みなんかするわけねえだろ!
もちろん正しくは、
「シー・スリーピーオー」
愛称(略称)はギリギリ、
「スリーピオ」表記を残すのも、
「黒歴史」正当化のために“やむをえず”か。
(※推奨は、いたしかねます)
——ということは、ずいぶん前にも書いた。
さて、バンダイプラモの1/12だが、
外形は、同じバンダイから2013年2月に発売された、
魂ネイション12''PM(12インチ・パーフェクトモデル)=超合金と完全に同じ。
目の下の凹みが、
実物は角の取れた幅広V字なのに、
目の下の凹みは曲線じゃなくて、思いっきり直線だぜえ。
↑これこそ造形担当のリズ・ムーアの天才性を示すところ。
↓12インチ超合金はU字。
——というのも前に書いたが、
とにかく同じ事は、
↓プラモにもガッツリと受け継がれてしまっている。
金属もプラスチックも、直せば光沢の表面処理が台無しになってしまうから、個人での修正は不可能。
もう一つ、超合金からそのままなのは、
「ロボット」(ドロイド)として、
↓プラモ(左)が、超合金(右)のデータの使い回しとわかる証拠写真。
関節を同軸線上に直結してしまっているところ。
↓サイドショウ1/6スケール(右)は、すねのパーツをヒザ間接から若干後にズラして、
あくまでも
↓人間が着込んでいる衣装
——だということを再現。
売り上げランキング: 435,794
このように、バンダイの3POプラモは、
単体でみても造形に難があるわけだが、
さらにR2-D2と並べると、別の問題、サイズ的なことも見えてくる。
↓どろぼうひげ氏の電飾モデルを、
↑似たような実物写真(1987年撮影)と並べると、プラモの3POは、R2に比して小柄なのがわかる。
大日本絵画
売り上げランキング: 9,912
R2-D2は、(メートル、センチ基準の国の人)ドイツ人が、
ブループリントと実測から、
二脚直立時の身長(体高)が107.8センチ(≒108センチ)と特定。
演じたケニー・ベイカーの身長112センチより小さいのは、
足を両脇の靴箱?に収めるために、脚をハの字に大きく広げて入るから。
1/12スケールだと、
108÷12=9
で、ちょうど9センチ。
なぜかバンダイプラモのR2は全高91ミリと、1ミリだけ背が高い。
(足底のローラーのでっぱりの1ミリか?)
とにかくR2のサイズは1/12として正確だから、3POが小さいことになる。
↑全高は142ミリ。
142×12=170.4
だから、
想定身長の170センチがそもそも低かったわけだし、
もともと140ミリ(168センチ想定)だったのを、
あわてて靴底を2ミリかさ上げして、帳尻合わせをしたらしい。
(上段左)1作目の実物の3POの足/(上段右)ボブ・バーンズ所有の1足。
(中段左)バンダイプラモ/(中段中)バンダイ魂ネイション/(中段右)サイドショウ
(最下段)バンダイプラモ
↓チャイニーズ・シアターに足形を刻む際、リック・ベイカーが足底を新規造形したが、外形はほぼ変わらなかった。
168センチ想定というのは、
WEG(ウエストエンド・ゲームズ)の1987年設定、
167センチから来てるわけだが、
フィート、インチでしか考えられないアメリカ人には、
メートル、センチ表示では感覚がつかめず、
167センチがどれだけ低いかが、さっぱり把握されていなかった。
とにかくこれが、
長く公式設定だったが、
新版のエンサイクロペディアから、
171センチに変更された。
LucasBooks (2008-12-09)
売り上げランキング: 171,614
今回の1/12スケールは、この設定に準拠してるというわけ。
だけどR2-D2の方は、
公式設定の0.96メートル(96センチ)に従う気は毛頭なかったのに、
どうして3POだけ、今さら卑屈に従う?
それになんで、
きっかり30センチの魂ネイション、
つまり6/1スケールよりも大きめのC-3POを、
2年前に出した同じバンダイから、
今頃になって、
1/12スケールにしては小柄な3POを、平気で出せてしまえるのか?
最近のルーカスフィルムは、
3POの実際の身長を175センチと言ってくるらしいが、
なにせ2.5センチ(1インチ)刻みでしかものを考えない、
アバウトな国民、
どうせ5フィート(152センチ)9インチ(23センチ)換算で決めたに違いない。
とにかくC-3POは正確な身長が、
これまで誰にも真剣に算定されておらず、
今回のバンダイも、その労力をサボっている。
以前に本ブログで、写真解析から174センチと出したが、
いまでもデカ過ぎる気がする。
解析を誤ったかもなと考える原因の一つに、
マーク・ハミル(ルーク役)もアンソニー・ダニエルズ(C-3PO役)も、
アメリカ、イギリスでは小柄なので、
身長は高め、つまり靴を履いて、公に姿を現す時の数値を公表してる。
——というのがある。
家の中でも靴履きがあたりまえの彼らにとって、
裸足の身長なんて、意味がないのだ。
なんにせよ、ダニエルズ氏の公称身長は、
173センチ(5フィート8インチ)である。
とか何とか書いてたら、前回の動画レビューで、
↓うんと引きの画のスチルが紹介された。これは再計算のチャンス!
R2は、高さ304ピクセル。
3POは、高さ489ピクセル。
304:489=90:x
x=144.7697....
つまり1/12スケールのC-3POなら、全高は145ミリ弱とすべきで、
その場合、145×12=174
実際の身長は、
174センチ弱(173.72)。
R2を107.8センチで再計算すると、
304:489=107.8:x
X=173.4019.....
となり、
173.5センチが最も近く、
12/1だと、144.6ミリが理想となる。
そんなこんなで、バンダイは全高約145ミリで、
ペッタンコ靴のC-3POにすれば、
R2-D2との釣り合いも、劇中どおりにできたわけ。
メッキパーツの造形と同様、
これまたモデラーには修正が不可能だから、
本製品に対する、「なんだかなあ」感、
残念感が、私にはどうにもぬぐいきれないのであった。
それにバンダイの1/12スケールプラモは、
これで4種類でたわけだが、
ドロイドコンビの大きさ対比に問題があるだけでなく、
先行したベイダーとトルーパーの造形の方向性とまるで異なり、
↓せっかく揃えて並べても、
↑シリーズとしての統一感がまるでないのも、どうかと思うよ。
↓ドロイドコンビとベイダー、トルーパーが一同に会した公式スチルは、
↑この時(Tシャツアイロンプリント集)の一連しか存在しません。
バンダイのSWプラモ、
次回はたぶん、
↓これです。
売り上げランキング: 1,056
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
Mad Max: Fury Road
ここ数年、
前評判の良い映画に限って、
自分には期待はずれということが多く、
昨年でその最たる例は、
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』だった。
熱狂に水を差すとブログが炎上しかねないので、
去年は黙っていたが、
ようやく何がダメだったかを指摘すると、
突き詰めが甘く、
せっかくの素材が生かされていないから
——ということに尽きる。
アライグマのキャラ(名前すら覚える気なし!)が象徴するように、
見かけはまったく冴えず、
とうてい大任を果たせそうもない顔ぶれが、
意外な活躍で、存亡の危機を救う。
——という筋立てだったら、
当然ギャップや意外性を演出する仕掛けが欠かせないはずで、
予告篇はそこをくすぐっているのに、
肝心の本編にはそういう伏線や下地作りがどこにもみあたらず、
淡々と即物的な描写の積み重ねが続くだけで、
映画が有機的に機能していない(=生き物として息づいていない)こと、
このうえなし。
こんなので喜べるのは、
ユーチューバーの動画を喜ぶガキンチョレベルの感性と知性で、
想定観客層の中高生あたりがせいぜいだろうと感じたが、
いい年こいた大のオトナまで手放しのベタ褒め状態で、
「俺たちのための映画」に認定するに至っては、
ひとごとながら、「おいおい、きみたち大丈夫か」と心配になった。
監督のジェームズ・ガンは、観客をナメているんじゃ、
とさえ勘ぐったが、
こう言う場合、
『トランスフォーマー』シリーズのマイケル・ベイと同様に、
監督の知性感性が想定観客のガキンチョレベルか、
時にそれ以下なだけだったりする。
という去年があったので
なんだか周囲は公開前から異様に盛り上がっている
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
だって、実際に自分の目で見るまでは、
他人の評価はあてにならないと、
用心に用心を重ねて、
7月1日に、
『ハンガー・ゲーム FINAL: レジスタンス』の前座として、
2D字幕版で鑑賞。
別に『マッドマックス』が『ハンガー・ゲーム』の前座になったのは、
シネコンのタイムテーブルの都合だが、
鑑賞前の期待値は、意図的に低めに設定していたのも事実。
で、いざ実際に見てみたら…。
まぎれもない傑作!
今年は映画をほとんど観てないから、
年末の『スター・ウォーズ フォースの覚醒』を観ないうちから、
2015年ベストは早くも確定。
生涯でもベスト級!
「まだまだ映画でやれることがあるんだ」
と、新たな可能性を示し、
「映画とは、かくあるべし」
を堂々と示した、
真に映画史に残る傑作です。
ドラマ自体にも胸を打たれたが、
7割~8割方進んだ時点で、
映画自体の鮮やかな出来の良さに、はやくも感涙が止まらず、
そのまま滂沱(ぼうだ)の涙で、
上映館を出る羽目に。
この涙は、
『ヘアスプレー』(2007)
『ダークナイト』(2008)
——以来の、数年に一度、あるかないかのものである。
始まってからずっと、
今まで見たこともない映像で、
これまで聞いたこともない(=前代未聞な)話が、
テンポ良く語られ、
観客はグイグイと引きこまれていく。
とにかくスキの無い映画で、
◎脚本
◎撮影
◎編集
◎セット
◎プロップ
◎衣装
◎メイク
◎キャスティング
◎役者の演技
◎VFX
◎サウンドデザイン
◎音楽
——と、およそあらゆる構成要素が緻密に計算され尽くし、
しかも計画倒れや消化不良に終わることなく、
きちんと役目を果たし尽くしている。
つまり
「ガーディアンズ~」とは、ことごとく逆を行ったからこそ、
「マッドマックス 怒りのデス・ロード」は成功したとさえいえる。
さりとて、中途半端な巨匠監督にありがちな、
「ねえねえ、ボクってすごいでしょ」という、
これみよがしなテクニックの自慢大会に堕すことなく、
売り上げランキング: 12,305
全ては観客を満足させるためのサービス精神にもとづくものだというのが、
画面からひしひしと伝わって来るので、
ジョージ・ミラー監督がこの作品を作ってくれたことに、
ひたすら感謝の念でいっぱいになる。
いやあ、この映画を観るまで、生きてて良かった!
(以下ネタバレ 赤字部分)
結局これは、人間の可能性と希望の物語。
冒頭で、絶望しかないような未来の地獄図が描かれ、
その状況は圧倒的に絶対で、
とうてい変えようがないように思われる。
しかし、
「人間は、そんなにヤワなもんじゃない」
「生きている限り、希望は必ずある」
と示すように、最後まであきらめなかった者が勝利する。
最後に勝つ者は、登場時の様子からは思いもよらない変化と成長が、
旅を続けることで訪れ、しかもその変化は、他者との関わりでこそ、もたらされる。
反対に負ける者、滅びる者は、変化も成長も見られず、
かたくなに最初のままの自分を押し通す。
そして変革の最大の功労者は、
無名の民から出(い)で、
勝利の後も権力をむさぼることなく、
再び無名の一人として、その場を去って行く。
(ネタバレおわり)
ともすれば大上段にかまえて説教臭くなりそうなこの作品に、
適度なジョークや茶目っ気を随所にふりまく余裕にも恐れ入った!
たとえば日本なら
「激おこプンプン丸子(げきおこぷんぷんまるこ)」
とか
「怒り心頭子(いかりしんとうこ)」
とでも置き換えられそうなキャラ、
フュリオサ(シャーリーズ・セロン)の名前が、通り名ではなく本名だとか、
「んなわけねえだろ!」も、わざとそこここにちりばめられている。
中盤あたりから、
「この映画に文句をつけるヤツなんているのか?」
と思ったが、
後でチェックした、否定意見はたいてい、
「やはり『マッドマックス2』(1981)は越えない」
売り上げランキング: 985
とかいう、
『ダークナイト』を見た後でも、
「やはりバットマン映画の最高峰は『リターンズ』(1992)」
売り上げランキング: 76,002
——というのと同じ、
かたくなに自分を変えない者だというのが、
皮肉と言おうか何と言おうか…。
私は最近、3D映画という選択肢がなくなったこともあり、
2Dで作品の魅力がなくなる映画だとは思わないし、
極力デジタル効果を避けて、本物の迫力で押し通した本作のスケール感は、
「ルーカスも『エピソード1』(1999)のポッドレースのシーンを、
ホントはこういう風にやりたかったんとちゃうんか!」
って感じで、2Dでもいささかも減じなかったが、
とはいえ、
家のテレビで見る作品じゃないことだけは確かです!
絶対にお見逃しなく!
【予告篇】アンドルー・プロバート/フェイズ2のエンタープライズ〈その4〉
デアゴスティーニ・ジャパン (2015-07-14)
1年以上前、2014年6月28日付けの記事、
これ(マット・ジェフリーズ/フェイズ2のエンタープライズ〈その3〉)の続き。
あまりに間が開きすぎたので、
おさらいすると、
平面デザインを、元祖エンプラをデザインしたマット・ジェフリーズが、
立体造形を
↓ブリック・プライスと、
↑ドン・ルースが手がけた、
「フェイズ2」版エンタープライズ改装型は破棄されたが、
同企画が、劇場用作品『スター・トレック』に昇格した際、
売り上げランキング: 25,323
映画版エンプラの「芯」として、息を吹き返すことになる。
ここでの立役者は、アンドルー(アンドリュー)・プロバートなんだが、
今では本人のサイトも確立。
前の記事から1年以上、
フェイズ2エンプラがらみの最新記事(2014年12月8日)からでも、
半年以上もブランクがあったのは、
近年プロバートが積極的にインタビューに応じ、
そのネット記事が豊富なため、
まずはそれらを読みこなさないと、
中途半端な書きようにしかならないと悟ったから。
しかし、「メンドクサイから後回し」してるうちに、
いたずらに時は過ぎ、
今日まで“おいとま”が続いてしまった。
今回再開したってことは、
きっかけになる情報が公開されたわけ。
それがトレックヤーズ(Trekyards)の最新動画で、
2015/06/26 に公開
その内容は驚愕に満ちていた!
2015/07/03 に公開
あわてて探してみたら、
他にも動画インタビューに答えているのが見つかった。
2013/06/14 に公開
これらを訳して記事にまとめるには、それなりに時間がかかるので、
それまで3つの動画を堪能しておいてください。
英語だけど、興味のあることなら、
言ってることは、だいたいわかってくるもんだよ。
Voyageur Press
売り上げランキング: 160,253
ゼロダークネス/【補完】何人いるの、ウルトラマン?〈その17〉
売り上げランキング: 418
いよいよ7月14日からスタートする、
ウルトラマンX
——を全ウルトラマンリスト(何人いるの、ウルトラマン?)に加える前に、
もらしていた2種類のウルトラマンにも、
言及しておかなければ。
1人目(1種類目)は、
ゼロダークネス(2013)
売り上げランキング: 34,015
2人目(2種類目)は、
ビクトリーナイト(2015)
売り上げランキング: 2,279
どちらも新たに人数が増えるのではなく、
既存ウルトラマンと人格は同じなので、
あくまでもバリエーションに過ぎないが、
かといってスルーというわけにもいかない。
まずは1人目のゼロダークネスだが、
これを取り上げると必然的に、
芋づる式に、ベリアルとゼロのバリエーションに触れることになる。
売り上げランキング: 1,392
売り上げランキング: 11,561
ゼロダークネス
『ウルトラゼロファイト』第2部「輝きのゼロ」に登場。
身長:49m
体重:3万5000t
バラバラになったアーマードダークネスから抜け出たベリアルの魂が、ゼロの体に乗り移った姿。
そのため肉体はゼロのものだが、身体のラインや体色がベリアルに似たものに変化し、ウルティメイトブレスレットも黒く染まっている。
意識は完全にベリアルが支配しているため声もベリアルのものになっており、ゼロの意識は周りの状況が見えるだけで一切手出しできない状態となっている。
その戦闘力は凄まじく、ゼロの武器や技も使いこなしている。
……。
「アーマードダークネス」って、なんじゃらほい?
暗黒魔鎧装(あんこくまがいそう)
アーマードダークネス
売り上げランキング: 101,678
エンペラ星人の配下が皇帝に献上した暗黒の鎧で、エンペラ星人がウルトラの星に再び侵攻する際に装着する予定だった。
エンペラ星人の本拠地でもあった惑星「ダークプラネット」に隠されており、装着した者には全宇宙を支配できるほどの強大な力を与えると言われているため、これを手に入れようとする多くの凶悪宇宙人たちがウルトラ兄弟と争奪戦を繰り広げる。
しかし一部でも身に着ければ強力な力を発揮できるものの、エンペラ星人以外には鎧の力を使いこなせず、装着した者を即座に吸収する。
とにかく、このアーマードダークネスを着込んだベリアルを、
暗黒大皇帝
カイザーダークネス
——と呼び、
①アーリーベリアル
②ベリアル
③カイザーベリアル
④アークベリアル
——に続く、ベリアルの第5形態とする。
売り上げランキング: 60,816
アナザースペースでゼロに倒されたベリアルの魂が、怪獣墓場でアーマードダークネスに宿り復活した姿。
バット星人グラシエやダークネスファイブ(メフィラス星人・魔導のスライ、ヒッポリト星人・地獄のジャタール、テンペラー星人・極悪のヴィラニアス、デスレ星雲人・炎上のデスローグ、グローザ星系人・氷結のグロッケン)が「あのお方」と呼んで仕えていた黒幕の正体で、姿を現して以降はカイザーベリアル時と同様に「陛下」と呼ばれている。
売り上げランキング: 191,873
外見は首から下がアーマードダークネスになっており、魂だけの存在のためカイザーベリアル時にあった顔の右側の傷が無い。
また、声は以前より低くなっている。
アーマードダークネスと一体化したことで更なるパワーアップを遂げており、アーマードダークネスの武器を駆使し、その戦闘力はストロングコロナゼロとも互角に渡り合うほど。戦闘中もゼロを挑発する余裕を態度を見せたほか、ゼロとの戦いを楽しんでいるそぶりを見せるという、ゼロをして「ドン引き」と言わしめるほど狂気じみた一面も見せた。
売り上げランキング: 94,003
スライによって会う資格があると認められたゼロの前にアーマードダークネスの姿で現れた後、自らその素顔を見せてゼロを驚かせ、戦闘に突入。
激闘の末、ウルティメイトゼロのウルティメイトゼロソードで胸を貫かれてバラバラに砕け散るが、宿っていたアーマードダークネスを破壊されただけであり、直後に抜け出たベリアルの魂が一瞬の隙を突いてゼロの体に憑りつき、ゼロダークネスへと変貌した。
売り上げランキング: 97,357
ゼロダークネスは、アナザースペースでのウルティメイトフォースゼロとダークネスファイブの戦闘に、青黒いオーラを纏(まと)って乱入。
圧倒的な強さでジャンボット、ミラーナイト、ジャンナイン、グレンファイヤーを次々と瞬殺し、ゼロの意識にも自らの手で仲間達が倒れていく様を見せつけて光を失わせることで、一度はウルティメイトフォースゼロを全滅に追いやった。
売り上げランキング: 13,374
売り上げランキング: 11,839
売り上げランキング: 43,662
売り上げランキング: 21,459
しかしゼロの意識が仲間達の魂やピグモンに呼びかけられて復活し、活動を停止。
ベリアルの魂が追い出されて、シャイニングウルトラマンゼロへと覚醒を遂げる。
シャイニングゼロ
『ウルトラゼロファイト』第2部から登場。
身長:49メートル
体重:3万5000t
ゼロの最強形態で、輝きのゼロとも呼ばれる。
体色は金と銀を基調とし、目とビームランプは青。カラータイマーは五角形のシャイニングエナジーコアに変化し、ウルティメイトブレスレットは体と完全に一体化、胸と肩のプロテクターがなくなった代わりに全身のボディラインにその意匠が見られるなど、外見は大きく変化している。
売り上げランキング: 60,922
映像に先駆けてゲーム『ウルトラマン オールスタークロニクル』にも先行登場しているが、誕生の経緯は異なり、カイザーダークネスによって奪われたウルトラ戦士達のウルトラスピリッツがゼロに集まり誕生した希望の戦士とされている。
売り上げランキング: 10,438
さて、ベリアルはどうなったかというと、
肉体を失ったベリアルの魂は実体を維持できなくなり一度は消滅したが、エピローグではシャイニングゼロがウルティメイトフォースゼロを復活させるために使ったシャイニングスタードライヴによる時間逆行の影響で、ベリアルも本来の肉体を取り戻し、完全復活を遂げている。
——以上が、「ウルトラゼロファイト」での展開で、
売り上げランキング: 10,827
完全復活したベリアルは、
『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦!ウルトラ10勇士!!』(2015)
にも、本作の敵であるエタルガーがゼロの記憶から生み出したエタルダミーとして登場。
売り上げランキング: 1,828
オリジナル同様の長い鉤爪状の手を使った格闘術を武器に、時空城の第四階層でゼロと激闘を繰り広げる。
売り上げランキング: 3,118
最後はストロングコロナゼロのウルトラハリケーン、ガルネイトバスター、ルナミラクルゼロのミラクルゼロスラッガー、シャイニングウルトラマンゼロのシャイニングエメリウムスラッシュを立て続けに食らって倒された。
売り上げランキング: 101,676
ああ、ややこしい。
最近はアレだね。
モード違いやバリエーションにも、
いちいち設定や、そのキャラ成立過程が欠かせなくなっているんだね。
そんなこんなで、ビクトリーナイトについては、またいずれ。
クロノス・ワン【附記】/こだわる理由Ⅴ: 1/537エンプラ補完計画〈その26〉
デアゴスティーニ・ジャパン (2015-07-14)
2つ前のスタトレ記事
(クロノス1〈カティンガ級〉【後編】こだわる理由Ⅳ:
1/537エンプラ補完計画〈その26〉)で、
現行ラウンド2のカティンガ級1/537スケールキットをベースにした、
売り上げランキング: 248,396
「クロノス1(ワン)のまともな完成作例を、
見たことがない」
旨を書いたが、
YouTubeに、
↓こんな動画が!
2014/06/18 に公開
投稿元の、
ダム・ウインド・デザインズ
(DaM Wind Designs 以下DMD)
と言う名前をフェイスブックで探したら、
主宰のデビッド・M・ウィンダム(David M Windham)の作例写真の数々が、
こ…これはスゴイ!
え?
なんだかノイズが盛大で、
よくわからない?
いや、まだまだこれからですよ。
↓エッチングパーツはフェドーラトロン。ブリッジのディテールアップパーツはJTグラフィックス。
↑ブリッジ後端の士官ラウンジの小窓も、フェドーラトロン。
改造パーツを買いそろえれば、
同じレベルで、誰でもできるわけじゃない。
(上)主船体の鳥の羽根を模した凸部は全て削り落とし、パネル凹ラインは“けがき”直して、さらにプラ板を貼って凸モールドを復活。
(中)主モールドだけでなく、各所に配されたレリーフ状の装飾も、エッチングで抜かりなく再現。
(下)JTグラフィックスの改造パーツには、不透明版とクリアパーツ版があるが、DMDはあえて不透明版を選択。両端からチップ型LEDで照らして、全体がグリーンの帯状に発光する様子を再現している。
ではDMD版は、実物のスタジオモデルに、どれだけ肉薄しているのか。
まずは劇中(『スタートレックVI 未知の世界』)との比較。
ぱっと見、判別がつかないソックリぶり。
売り上げランキング: 76,768
代表スチルとの比較。
次に各所のアップ。
※基本的に大判画像は、DMDのキット作例。
小さい画像は、実物のスタジオモデル。
↓ブリッジ
完全に同じではないが、その差違はもはや、間違い探しレベル。
↓ブリッジと主船体の連結部
↑主船体翼部のエッジ。
↓後部インパルスエンジン周辺。DMD版は、なぜか光子魚雷発射管がふさがれている。
↑艦底の複雑なデコレーション。
↓翼部の紋章とクリンゴン語の艦名表示。
↑ワープナセル外側・側面。
※ホントに「クロノス1」と書いてあるわけではなさそうだが、(IMMLNKJ?)、実物どおりなのは確か。
↓屋外で撮影された、スタジオモデルのワープナセル外側後端。
↑DMDのキット作例の同じ部分。
実物のクロノス・ワンのスタジオモデルは、
スタートレック40周年の2006年のオークションで売却されてしまい、
おいそれとお目にかかれるものではない。
となると、現在目にできる世界最強のクロノス・ワンのレプリカモデルは、
このDMD版と言うことになるだろう。
DMDのデビッド・ウィンダム氏は、
↓クロノス・ワン以外にも、
↑多数の完成作例を展示会で披露。
↓中にはこんなものも!
こ…これは!
というところで、明日の記事(テーマ:スター・ウォーズ)に続く。
AT-STモデルチェンジの真相(前編)/〜にまつわるエトセトラ〈その6〉
『帝国の逆襲』(1980)版スカウト・ウォーカーについては、
さすがにもう語り尽くしたので、
【1回目】
【2回目】
【3回目】
【4回目】
【5回目】
「AT-ST」と改称された、『ジェダイの復讐』(当時邦題・1983)版に話を移すが、
『帝国』版と『ジェダイ』版が違うのは良く知られていても、
●実際にどこがどう違うのか
●なぜ同じにしないで、変えたのか
——については、知らない人が多いのでは。
似たようなアングルで撮影された資料写真を並べれば、
形の違いはよくわかるが、
大きさの違いは、まったく把握できない。
ルーカスフィルムのアーカイブ(資料庫)に現存する、
『帝国』版と『ジェダイ』版モデルを並べて写真に収めるなんてのは、
まず望み薄。
というのも『帝国』版モデルは、
『ジェダイ』のストップモーション(コマ撮り)アニメの
テレマティックス(ビデオによるテスト映像)に使用され、
↓「ぜんぶスター・ウォーズ」(週刊ヤングジャンプ特別編集)でしか見たことのない、貴重な資料写真。
私が1992年に訪問したスカイウォーカーランチの資料庫では、
整理棚の一番下に、小動物の死骸みたいに横たわっていて、
とうてい人前にさらせない状態だった。
いたましい姿はともかく、
ぱっと見は、ケナーのトイと印象が変わらないサイズと外形だったのを覚えてる。
↓『帝国』モデルと人との対比は、こんな感じ。

↑2014年5月に、ダース・ベイダー役のデビッド・プラウズと共に。
2014年に撮影されたモデルは何かというと、
ジェイソン・イートン氏が2010年に発表した、
完璧に復元されたレプリカを参考に、
世界中で続々と完成された、モデラー自作のクローンモデルの一つ。
↓昨日紹介した、
↑DMD、デビッド・ウィンダム氏の作例も、その一つ。
↓全世界で続々と産み出される、プロップレプリカのクローンたち。
イートン作の復元モデル完成第1号は、派手なアクションポーズのため、
資料写真との比較が困難。
↓そこで立ちポーズの後続モデルをここに紹介。
↑いくつかの流用パーツが揃わず、塗装も途中とのこと。
ただし高い工作技術に加え、
高価な絶版キットの流用パーツを、全て買いそろえなければならず、
知識や情報だけでは、完成には行き着かない。
イートン氏が流用パーツ解析に利用した、
ILMでの撮影終了直後の、
(状態が完ぺきで、ネコやニワトリの死骸と化してしない)
スタジオモデル各部を接写した資料写真は、
ネットには非公開で、一般には閲覧不可だから、
↑フットパッド(足/靴)は、↓
↑MPC社のプラモ、ダース・ベイダー専用タイ・ファイターのボディ下部のパーツを、斜めにカットしたもの。
こうした復元モデルで、
代用閲覧するしかない。
↑クローンモデル右側の細部塗装がないのは、
本物のスタジオモデルもそうだったから。
実物モデルを製作したのはジョー・ジョンストンで、1作目のサンドクローラー等、劇中で映らない側は未塗装、未完成で済ませるように、モデル制作担当者に指示を与えることも多かった。
とにかく、こうしたクローンモデルの1つを、
やはり自作の『ジェダイ』版AT-STと並べて撮影したフランス人
(パリ在住のムッシュー・トクス=MonsieurTox)がいるので、
『帝国』版は組み立て途中だが、ここにご紹介。
『帝国』版の頭の大きさは、『ジェダイ』版の半分しかない。2009年公表。
この大きさに間違いがなく、正確だと判断できるのは、
モデル各所に貼り付ける、プラモの流用パーツの大きさが確定していることとの兼ね合いから。
では、この大幅な形状変更は、どうして行われたのか?
本来は『ジェダイ』にも、『帝国』版をそのまま出す予定で、
ジョー・ジョンストンが描いた、
↓一連のイウォーク族のゲリラ戦アイディアスケッチでは、
最終稿の二つ小窓型でなく、
AT-ATと同じ、
横スリット型の展望窓タイプだが、
↓おそらく最終スケッチの小窓2つデザインを、
描いた本人が忘れていたらしい。
一方で、デザイン過程と無縁だったラルフ・マクォーリーの方は、
小顔で脚長の『帝国』版モデルに忠実に描いている。
↓なのにどうして?
——というところで、続く。
ビクトリーナイト〈その1〉/【補完】何人いるの、ウルトラマン?〈その18〉
これ(ゼロダークネス/【補完】何人いるの、ウルトラマン?〈その17〉)の続きで、
これまで本ブログの全ウルトラマンリスト、
何人いるの、ウルトラマン?
から漏れているウルトラマンをあぶりだす、2015年第2弾。
ビクトリーナイト
あれえ、最新のX(エックス)も紹介したんだから、
その前に取り上げなかったっけ?
——と思ったら、円谷ファンクラブ会報の表紙で、
35号のギンガビクトリーに続く36号に登場してるので、
ビクトリーナイトの方が後続で、
どうやら混乱、混同してるうちに、
扱う機会を逃したらしい。
ビクトリーナイトは、
形態はビクトリーと同じで、単なる色替え。
カラリング変更の理由は、ビクトリーの玩具が期待したほど売れず、
売り上げランキング: 4,822
同じ金型で商品を再展開する必要に迫られたから、
というのがホントのところなんだろうが、
ボディのメインカラーが、
ブラックからブルーに変更された理由も考えてみる。
黒いウルトラマンと言えば、
発想の原点は、レオのNGデザイン流用のバルキー星人(1974)で、
↑タロウが黒いのは、石油を全身に浴びてるからで、悪に染まったからではありません。
売り上げランキング: 187,930
本格的な潮流は、
↓ウルトラマンシャドー(1997)に始まり、
↑よく見るとブラックじゃなくて、ミッドナイトブルーかダークパープル。
↓イーヴィルティガ(1997)や、
“EVIL”(イーヴィル)とは“邪悪”のこと。
一説によれば、悪は生きることに背くから、“LIVE”の逆さ綴りなんだってさ。
売り上げランキング: 17,188
↓ティガダーク(2000)、
ティガダークは、ティガ本人の太古の人格なので、完全な悪のウルトラマンというわけではない。
ただし「ギンガ」には、完全な悪役として登場。
売り上げランキング: 17,530
「コスモス」には、秩序、平和を意味する“コスモス”と対立する概念、混沌、騒乱を示す“カオス”を冠する裏ウルトラマンが登場。
↓カオスウルトラマン(2002)や、
↑カオスウルトラマンカラミティ(2002)、
↓カオスロイドU、カオスロイドS、カオスロイドT(全て2005)。
カオスロイドU・S・Tのデビューは、2005年のゲーム「ウルトラマン Fighting Evolution Rebirth」のCG像。スーツは各地のステージショーに、2007年頃より登場。
↑左から、カオスウルトラマン、カオスロイドT、イーヴィルティガ、カオスロイドS、カオスロイドU。すべてバグレー(バグ霊)。
カオスロイド3人の劇中デビューは、この『ウルトラマンギンガ 劇場スペシャル ウルトラ怪獣☆ヒーロー大乱戦!』(2014)。
光の国のウルトラマンのカオス化と共演で、バルタン星人、『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』(ムサシが登場)『ウルトラマンサーガ』に続き、またしてもコスモスの宇宙(コスモスペース)とM78星雲のウルトラ戦士の世界がつながった。
売り上げランキング: 162,650
「ティガ」以降、ごぶさただったダーク=闇の戦士の概念が、「ネクサス」で復活。
↓ダークファウスト(2004)
↑ダークメフィスト(2005)
↓ダークメフィスト(ツヴァイ・2005)
↓第32話にたった1回登場。眼光が黒から赤に変わった以外は、メフィストと何も変わらないツヴァイの存在意義は、赤目のダークザギにつなげることだったのかも。
「ネクサス」本編登場はファウスト、メフィストより後だが、ザギは2004年のNプロジェクト第1弾「ウルトラマンノア」雑誌展開からのキャラ。
↑ダークザギ(2004)
↓ウルトラマンダークとセブンダーク(2013)
↑マンダーク、セブンダークは、「ギンガ」より前に、銀座博品館劇場『ウルトラヒーローバトル劇場 第12弾』(2009)で、ウルトラマンガイスト、ウルトラセブンガイストとして登場している。
ガイスト(geist)とは、ドイツ語のゴースト(亡霊)。ゴーストバスターズは、ドイツでは「ガイスターイエガー」(GEISTERJÄGER)
売り上げランキング: 5,301
売り上げランキング: 91,865
ベリアル(2009)
売り上げランキング: 11,436
売り上げランキング: 55,588
売り上げランキング: 62,936
カイザーベリアル配下のロボット兵士のプロトタイプ、
↓ダークロプスゼロ(2010)
↑その量産型ダークロプス(2011)
売り上げランキング: 95,138
「ダーク」がついても、ダークロプスだけは他(ティガ、ファウスト、メフィスト、ザギ、マン、セブン)とは毛色が違い、生命体やその怨念ではなく、シャドーと同じくロボット。
なので正確には、「シャドーロプス」と考えた方がよい。
カイザーダークネス(2013)
売り上げランキング: 25,256
ゼロダークネス(2013)と、
売り上げランキング: 23,026
黒いウルトラマンは、
どうせ悪いヤツに決まってるという、一般イメージから行って、
ビクトリーは完全にアウトだった、
——というのもあるだろう。
では体色がブルーになった理由とは?
——というところで、〈その2〉に続く。
ギャラクティカ【前編】アンドルー・プロバート〈その1〉
ここ(【予告篇】アンドルー・プロバート/フェイズ2のエンタープライズ〈その4〉)
で予告した本編で、
プロバートが改装型エンプラ、
俗に言う映画版エンプラのデザイナーに起用されるまでの経緯を追う、
連載企画の、本編第1回。
今回は、プロバートの映画業界入りのきっかけについて。
なので、テーマは、まだ行き着かない「スタートレック」でなく、
きっかけとなった、「スター・ウォーズ」です。
1977年のこと、
プロバートはパサデナ(Pasadena)にある、
アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン
(Art Center College of Design)という、
日本なら総合美術大学(美大)にあたる学校に通っていた。
ほどなく映画『スター・ウォーズ』が公開され(5月25日)、空前の大ヒット。
雑誌には特集記事があふれ、
映画のスチルと共に、
ラルフ・マクォーリーのプロダクションペインティング(設定画)も、
多数紹介されていた。
プロバートは幼少期に、
母親が辞書の前後に製版の都合で差し挟まれる、
白紙のページを切り取って渡してくれたのをノートやスケッチブック代わりに、
覚えている限り最初に描いたのが、
イナズマ模様のフラッシュゴードンの宇宙船だったという、
筋金入りの宇宙船マニア、SFマニアだっただけに、
マクォーリーのイラストにすっかり心酔。
この人に会ってみたいと考えた。
するとマクォーリーは、“ロスを拠点とするアーティスト”と記されている。
オタク心を抑えきれないプロバートが地元の電話帳で探してみると、
あっさりとマクォーリーの電話番号が見つかった。
臆せずにさっそくかけてみるのが、オタクの度胸とでも言おうか…。
プロバート「もしもし」
「はい」
プロバート「あの…ラルフ・マクォーリーさんのお宅ですか?」
「そうだよ、私だが」
プロバート「えっと…アンドルー・プロバートと申します。うちの大学の新聞でインタビューしたいんですけど」
マクォーリー「どこの大学だい?」
プロバート「アートセンターです。パサデナの」
マクォーリー「ほう、私も昔、あそこの学生だったんだよ。だったらうちにいらっしゃい」
若きマクォーリーは朝鮮戦争に出兵。
彼を見下ろす朝鮮兵に銃口を向けられるも、
なぜかその兵士は引き金を引かずに立ち去って命拾いした。
生き延びたことをムダにしないように、
絵がうまいという自分の才能を生かすべく、
パサデナのアートセンターに入学。
↓さかのぼれる、最も若いラルフ・マクォーリーの近影。
↑若き日のシド・ミード。どちらもアートセンター時代のものではない。
同じ時期に4歳年下のシド・ミードも在籍していて、
当時からバツグンの才能を発揮していたと、
作品集DVDのインタビューで、マクォーリー本人が語っていた。
↑新国立競技場の案ではなく、シド・ミードの宇宙船案です。
こうしてプロバートはマクォーリーと知りあい、
自己紹介を兼ねて自分の作品を見せ、
きちんとインタビューして、
それは学校新聞の記事にまとまった。
1977年末から78年の年明けの頃。
プロバート「冬休みに働きたいんですけど、デザインの仕事、ありませんか」
マクォーリー「ちょうど今、『スターワールド』っていう企画が進んでて、ヘルメットのデザイナーを探してるよ」
プロバートはマクォーリーの推薦で、
当時のILMの主任、ジョン・ダイクストラの面接を経て、
ヘルメットのデザインを提出。
ジョー・ジョンストンの案とのコンペになった。
↓フィルム缶を3つ並べて芯にした宇宙船、リヴァリー(Livery)の原型を手にするジョンストン。
↑この宇宙船は、鉱石運搬船、ミネラルシップと設定された。
脚本では、主役と敵側は宇宙の各地を転々とし、
様々な星と交流するので、
すでに確定していた
↓主役側のヘルメットデザインが、
↑地球のエジプト文明に影響を与え、
↓敵側のデザインは、
↑ギリシャ文明に影響を与えたと仮定して、
トサカのあるデザインを描いた。
スリット状のバイザーが、ヘルメットの端から端まで広がっているのは、
劇中に登場する、ロンパリの爬虫類風エイリアンが、かぶるんだろうと想定していたため。
とにかくプロバートは、
↓メットのデザインを完成させ、
一方、
↓ジョンストンのデザインは、
↑日本の足軽鉄砲兵や、忍者みたいなものだった。
『スターワールド』のプロデューサー、
グレン・ラーソンの息子(まだ子供)が選んだのは、
プロバートの案だった。
こうしてアンドルー・プロバートは、
ILMに在籍することになり、
「スターワールド」から「バトルスター・ギャラクティカ」に改題された企画に、本格的に関わることになる。
売り上げランキング: 65,686
スターワールドという仮題は、
「ギャラクティカ」のパイロットエピソード、
“Saga of a Star World”(星の世界の伝説)に、痕跡をとどめている。
売り上げランキング: 66,314
また当初は、
「バック・ロジャーズ」と並行して企画が進んでいた。
続きはまた今度。
ウルトラマンX(エックス)第1話「星空の声」感想
さや姉(ねえ)の誕生日、
7月14日に放送された、
「ウルトラマンX」第1話
売り上げランキング: 329
水曜午後5時半からだった「ギンガ」(2013)
火曜の午後6時からになった「ギンガS」(2014)
——に続き、
テレ東のウルトラマンも、今年で3年目。
ようやく、
まともなウルトラマンの復活
です。
これから、どこがどうよかったのかを述べるが、
さいわい、来週の金曜夕方まで、
YouTubeで“再放送”されてるので、
未見の方は、まずはご覧になってからどうぞ。
では良かったポイント。
1.新味がある
とにかく前作「ギンガS」前々作「ギンガ」が、
色々と妥協の産物だったので、
今回もどうせ…と思ったら、さにあらず。
始めから終わりまで徹底的に考え抜かれ、
丹念に作り込まれていて、ひたすら感心、
ビックリした。
まずはその設定。
「ギンガ」以来のスパークドールズとドラマの融合だが、
「ギンガ」と「ギンガS」では、そもそもが玩具主導で、
「ソフビ怪獣と変身グッズの連携」が決まってて、
それにドラマが強引に結びつけられてるから、
話がヘンなこと、このうえなし。
正直、その仕組みは、なにがどうなってるのか、ちっともわからなかった。
「X」では、スパークドールズはオーパーツあつかい。
これが15年前(西暦2000年とは特定されない)に世界各地で実体化して、
(ウルトラ)怪獣と人類が初めて遭遇した、地球が舞台。
怪獣の実体化は、
太陽爆発のフレアが原因で、
そのフレアは、赤い玉に追われていた青い(紫の)玉が、太陽と激突して生じたもの。
この余波で赤い玉の正体、
ウルトラマンエックスも結晶化して、ガラスのように砕け散って四散。
15年間で確立された、人類の対怪獣デバイスを介して、
再び実体化、デバイスの所有者と一体となって蘇る。
売り上げランキング: 115
——という、きわめて理にかなったプロットで、
その世界で初めて人類が目にする、
全く新しいデフォルトのウルトラマンが紹介される。
なので「ギンガ」と「ギンガS」の珍妙な世界とは無縁。
そうなると、これまでパターンで続けて来たことが全て見直され、
●(マジンガーZみたいに)初めて合体した主人公の戸惑いと、立ち振る舞いのぎこちなさ
とか、
●それにともなう新しい見せ場
——が続出。
長年にわたり、
「ウルトラマンって、こういうもんでしょ」
と、盲目的にくりかえされたパターンがことごとく見直されていて、
タイヘン好感が持てた。
2.まともな防衛組織
「ギンガ」は 降星町(ふるほしちょう)という閉じた空間に限定された、箱庭的な物語で、防衛チームの出番なし。
続編「ギンガS」でも、地底にビクトリウム鉱石の眠る雫が丘(しずくがおか)にしか怪獣は出現せず、特捜チームUPGには車両しか装備がなく、隊員はヘルメットもかぶらない。
売り上げランキング: 38,035
売り上げランキング: 38,102
↓UPGには、パンサー尾形みたいな松本ゴウキ(加藤貴宏)がいたが、
↑特殊防衛チーム Xio(ジオ)にも、タカトシのタカや、しょこたんや、はんにゃの金田みたいな、パチモン臭い顔ぶれがズラリ。
それに対して新チームXio(ジオ)の隊員は、
ヘルメットとアーマーでフル装備。
3種の車両と合体する飛行ユニットと、万全の体制。
売り上げランキング: 1,176
ようやく説得力のある体制が整った。
3.存在感のある怪獣
怪獣描写もていねいで、パターンに堕さず、
一連の破壊シーンで、確実に被害者や犠牲者が出ていることが、
間接的ながら示されていて秀逸。
タイプG(=ゴジラ?)に分類され、
バーニングゴジラみたいな溶鉄怪獣デマーガは、
↓ゴアゴンゴンやミレニアムゴジラ、
↑アーストロン路線の、正統派の恐竜型。
売り上げランキング: 898
しいていえば、アーマーと合体する前の素体のエックスが、
生身のはずなのにメカメカしいのは、
つきつめて考えるとヘンな気がする。
売り上げランキング: 407
中断なしの全22回。
火曜日に見逃しても、金曜の夕方から1週間限定でYouTube配信があるので、
全話見通そうと、心に誓うのであった。
1/48 Xウイング【前編】/バンダイプラモ(11)
昨日もX(エックス)、今日もX(エックス)。
******************
バンダイSWプラモの、
検証第11弾は、
売り上げランキング: 848
1/48スケール
Xウイング・スターファイター
ムービングエディション
まずは、ウ“ィ”ングとかの、ィを小文字化なんぞというヘンな小細工や、
↓デビルウイングをデビルウィングと書いたら、
「なにカッコつけてんだよ」となるのと同じ事。
Xとウイングの間に、日本語では不要な、X-メンみたいなハイフンが入ってないのは、めでたい。
というのは前に書いたが、
旧三部作当時は「ファイター」(戦闘機)だったのが、
↓MPC(1977)→ERTL(1987)→AMT(2005)と、3ブランドを生き延びた、
世界初のXウイングのプラモは、一貫して「ファイター」
1987年以降、「スターファイター」(宇宙戦闘機)表記が増えてきたのが気になる。
スターファイターという用語が定着したのは、
↓あくまでも新三部作の商品から。
売り上げランキング: 73,688
売り上げランキング: 33,478
タイ・ファイターが、タイ・スターファイターと呼び直された例がないことからも、
Xウイング(や反乱軍の戦闘機)の方だけ改称するのは、本来おかしいことがわかる。
SW世界は、なにしろ宇宙こそが舞台なので、
「シップ」といえば宇宙船
「ファイター」といえば宇宙戦闘機
「ネイビー」といえば海軍ではなく宇宙軍
——に決まってるんだから、
わざわざ「スター」をつける必要ないんだけど…。
次に、「ムービングエディション」という、
ネイティブ英語ではまず見かけない、
和製英語の商品名も気になる。
アメリカ人もイギリス人も、
このギミックを「ムービングエディション」なんて、絶対に呼ばない。
「フルアクションモデル」とか、
“ULTIMATE ACTION PACK”が、いいとこでしょう。
電動で翼が開閉するギミックのあるXウイングのプラモは、
バンダイの前にもあった。
↑なぜかキャノピー開閉機構まで!
AMTにブランド移行したばかりの1998年に、
当時は最大サイズの、全長約39センチ(15.25インチ)で登場。
商品名は、
プロショップ エレクトロニック・Xウイング・ファイター
PRO SHOP Electronic X-wing Fighter
「プロショップ」は同時期のAMTのシリーズ名で、
↓USSヤマグチは、エンプラC型のクリア成型版
「上級者向けキット」の意味。
だからそれをのぞいた商品名は、単に「電動・電飾Xウイングファイター」と、
いたってシンプル。
とにかくムービングエディションなんてのは、
イングリッシュネイティブに言わせれば、
海外でヘンな漢字のTシャツを、
平気で着ているのと同じような感覚で、
バンダイという企業に、
国際感覚のある(=ホントに英語が出来る)エキスパートがいないのが、よくわかる。
SW模型の版権は、昔からテリトリー制で、
販売できるのは、許諾を受けた国内のみに限られている。
日本国内の流通なんだから、
英語はいいかげんでもかまわないと思うかも知れないが、
今や完全なネット社会で、
外国からでも日本製品専用通販サイトから、
気軽に買えるようになってるのに、
いまだに現状に対応する体制を整えないのは、
企業として怠慢ではなかろうか。
今回は、あくまでもパッケージングの話に終始したが、
次回はもっと本質的な、キット自体の問題について。
NMB・AKB希望の星/いきなりそっくりさん(46)
毎日更新をやめたため、
厳選した記事のみをお送りするようになった、このブログ。
実に久々の、くだらない冗談企画、
いきなりそっくりさん
その46回です。
今回のターゲットは、
渋谷凪咲(しぶや・なぎさ)。
2015年6月総選挙58位。
売り上げランキング: 106,223
並みいるNMB、AKB(てんとうむChu!)メンバーの中でも、
ひときわ光る存在感。
抜けるような色白で、
カメラが切り替わって彼女が映ると、
場の空気感がガラリと変わる。
パフォーマンスも達者で、
かわいらしく、ハツラツとしていて、
舞台映えがする。
売り上げランキング: 6,083
一方で、ド天然キャラで、
お寺の参拝が正しく出来るかのテストでは、
正面に映し出されたお寺の画像に、
「これ、私のお寺じゃない」と戸惑うスゴさ。
番組のクイズコーナーで最低のバカ子に決まり、
罰ゲームのはずのスカイダイビングを満喫したりと、
伝説や逸話にも、ことかかない。
さてこの、タレント性バツグンの渋谷凪咲。
なんとなく、昔から知ってるような、デジャヴな顔つき。
俗に言う「黒目がち」な顔つきの先輩と言えば、
小西真奈美なんだろうけど、
それじゃない。
スピッツ?
いやいや、確かに似てるが、
それを連想したわけでもない。
たしかもっと、ず~っと前の人だよ。
ああ、あれだ!
石森章太郎(石ノ森章太郎)の描く美人だ!
といっても
↓主役級の、楕円の瞳のネコ目の方じゃなく、
↑石森氏が漫画家になるのを後押ししてくれた、
姉がモデルと言われている、「竜神沼」のヒロインが始祖と思(おぼ)しき、
「黒目がち」どころか、
白目の全くない漆黒の目に星が宿った、
アニメ「009 超銀河伝説」のタマラに代表される
↓ゲストキャラに多い、美人の方。
↑ね、見立ては正しかったでしょ?
「ロボット刑事」には、このバリエーションで、
盲目を示すために、目の輪郭の中が白一色の令嬢も登場するが、
これも渋谷凪咲に通じるところ、多々である。
子供の頃は、石森キャラの、
↓主役男女のイケメンぶりには心酔しても、
↑男性キャラでは例がない、黒目だけの女性像をみるにつけ、
「なんでこんな、実際にはいない顔つきを描いたりするんだろう」
とフシギだった。
永井豪に、「常人の5倍のスピードで描ける天才」と評されるほどの、
世界で最も多作の漫画家、
石森章太郎(当時表記)の最盛期の原稿執筆ペースは猛烈で、
月650~700ページだったとも。
創作のピークで、氏の周囲の時空が歪み、
自分の死後の未来の女性、
渋谷凪咲の姿を見ながら、
それを原稿に描き写したのかとさえ、
思えてしまう。
——とかなんとか書いてたら、
くしくも最新の渋谷凪咲出演ラジオで、
「サイボーグ009」の話題が出るという、プチシンクロが!
以上、ひさしぶりの「いきなりそっくりさん」、
いかがでしたか?
laugh out loud records (2015-07-15)
売り上げランキング: 116
ウルトラシリーズ50年の生き証人
この記事(ウルトラマンX(エックス)第1話「星空の声」感想)
の執筆途中で、
長くなった部分をこちらに転載。
その際に取り上げた、「ウルトラマンX」第1話の動画公開も、
あと1日足らずの命なので、
くれぐれもお見逃しなく。
21日に放送された第2話「可能性のかたまり」は、
まあ、それなりでした。
円谷公式チャンネルで、「X」第1話に続いて、
2015年7月16日に公開された、この動画。
一切の断りもなく公開されたが、
最後の「7.7」の意味は?
円谷英二の誕生日記念映像にしては、公開は1週間以上遅れ。
2016年の7月7日(木曜日)に、
この映像で、シリーズ50周年記念映画を公開と言うことか?
だけど、巨大ヒーロー路線の元祖たるウルトラマンが、
なんでその影響を受けたエヴァの方なんかに寄せにゃならんの?
コカ・コーラ(創業1886年)が、
ペプシコーラ(創業1893年)の方なんかに、寄せたりしないだろ!
アイデンティティの崩壊だよ。
そういや、
『キャプテンハーロック -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-』(2013)
のCG映像初披露と、ほぼ同時に公開された、
東映の「ガイキング」CG映像も、
その後一切進展が聞こえてこないが、
とにかくハッタリだけの企画倒れは、
もうカンベン。
50周年といえば、
2013年もそうだったんじゃ、
と思う人もいるかもだけど、
それは、円谷プロ50周年。
来年の2016年は、
1966年1月2日放送開始だった、
「ウルトラQ」から半世紀。
「ウルトラ」シリーズ50周年であり、
同年7月17日から、
「ウルトラマン」が放送されたので、
2016年7月には、「ウルトラマン」シリーズも、50周年となる。
日曜夜7時の
タケダアワーで始まった、
「ウルトラQ」
当時4歳の、くしくも姓が“武田”のガキンチョは、
1月16日放送の、第3話「宇宙からの贈りもの」から、
本放送でシリーズを見続けている、
いわば歴史の証言者。
まさか「ウルトラマン」の新作放送を、
50年後も見ている羽目になるとはね。
とはいえ、さすがに中断なく、
50年も律儀につきあい続けたわけはなく、
実を言うと、シリーズで全話見たのは、
小6時に見ていた、金曜夜7時の「タロウ」(1973)までで、
「レオ」(1974)は中1で学習塾に通うため、
後半見られなくなった。
高3になった水曜夜7時の「ザ☆」(79)は、
裏の「ベルばら」を見てたので、前半まで。
大学1年時の「エイティ」も、ほとんど見てない。
だもんで後はもう、どうでもよくなって、
社会人になってもいたから、
海外ウルトラマンの
アニメ「USA」(1989)も
「グレート」(1990)も
「パワード」(1993)も
そもそもいつテレビで放送されたか知らないし、
本格的復活の「ティガ」(1996)も
「ダイナ」(1997)も、
「ガイア」(1998)もスルー。
土曜の午後6時じゃあね。
録画しようにも、当時住んでた場所は、
アンテナ状態が最悪だった。
そして「コスモス」(2001)からは、
映画版だけ見続けて、今に至る。
『ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT』(2001)
『ウルトラマンコスモス2 THE BLUE PLANET』(2002)
『ULTRAMAN』(2004)
なんでこんなに、
最近作を追わなくなったかというと、
テレビを見なくなったというのがそもそもあるが、
ウルトラのクオリティなんて、
最初の3本、
5歳で見ていた、
あくまでも始祖として偉大な、「マン」(66)
デザイン・SFドラマの頂点、「セブン」(67)、
10歳=小4で見ていた、
デザインはアレだが、人間ドラマが充実していた、
金曜夜7時の「帰ってきた」(1971)がピークで、
小5で見ていた「エース」(1972)で、
ウルトラ兄弟に頼り始めてから凋落が始まり、
あとはひたすら下り坂で、実に数十年、
今さら復権はありえないと見限っていたから。
「コスモス」以降の映画では
『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』(2006)
『大決戦!超ウルトラ8兄弟』(2008)は感心し、
『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』(2009)でピーク。
その後はダラ下がりのまま、
『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』(2010)
『ウルトラマンサーガ』(2012)
——を経て、今に至る。
とにかく、メビウスの映画2本と、
ゼロの最初の映画で「ウルトラマン」シリーズへの信用が回復し、
その後は本放送中に地デジ放送を見られる状況に復帰したので、
水曜午後5時半からだった「ギンガ」(2013)
火曜の午後6時からに変更された「ギンガS」(2014)
——に続き、
7月14日からは、
「ウルトラマンX」(2015)
を見続けている次第。
まとめると、
「ウルトラQ」の2要素、
「バルンガ」みたいなオトナむけに感心し、
「カネゴン」みたいなコドモ向けにガッカリするのをくり返して、
今に至るというわけ。
さすがに100周年を見届けることにはならないだろうから、
自戒を込めて言っておくけど、
みんなはこんなジジイに、なっちゃダメだぞ?
波動砲口を初めて語る「神は細部に宿るPART1」/蒼きヤマトへの憧憬(77)
マッグガーデン
売り上げランキング: 2,020
「神は細部に宿る(God is in the details)」は、
モダニズム建築の超高層ビルとして名高いシーグラムビルなどを設計した、
ドイツの建築家ミース・ファンデル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)
が好んで使っていた言葉。
しかし、誰が最初に言ったのかは、諸説あって良くわかっていない。
『素晴らしい芸術作品や良い仕事は、細かいところをきちんと仕上げており、
こだわったディテールこそが作品の本質を決定する。
何ごとも細部まで心を込めて行わなければならない』という意味。
ここから拝借。
うんとさかのぼると、
ギュスターヴ・フローベール(Gustave Flaubert)の、
「良き神は細部に宿る」("Le bon Dieu est dans le détail")までたどれるものの、
これまたフローベール自身の言葉ではなかったよう。
英語圏では、すでに廃(すた)れた言葉で、
代わりに「悪魔は細部に潜む」(the devil is in the details=あらゆる細部に落とし穴が潜む)が台頭している。
****************************************
宇宙戦艦ヤマト立体の理想形態の追及は、
その筋の達人たちによって今も進んでおり、
「2199」による再設定や、それに基づくバンダイ模型のプラモも、
あくまでも素材や芯としての、
途中過程としかあつかわれていない例が多い。
売り上げランキング: 3,129
とはいえ、そこまで来ると、
製品としての模型のどこがダメで、
修正や改造する根拠がなんなのか、
もはや「浅い」人間には理解不能なのも、また事実。
というわけで、それでもまだ、
画像を添えればわかりやすい例を中心に、
ここでまとめておこう。
今回注目するのは、
1.ブルワークとフェアリーダー、波動砲口
「宇宙戦艦ヤマト」(1974)がブームになって、
アニメのセル画のグニャグニャなヤマトに、
「ほんとにヤマトがあったら、
絶対こんな形じゃないよな」
——と感覚的にはわかっていたが、
再放送でヤマトブームが来て、
1977年7月25日にドラマ編LPレコードが発売されるに至り、
↓ジャケットこそ、いつもの「んなわけねえだろ!」ヤマトのセル画だったが、
↑内部の折り込みピンナップで目が冷めた。
スタジオぬえの加藤直之(※下図は宮武一貫と二人で仕上げたらしい)が着彩まで担当した、
リアルタイプイラストは、
「ヤマトが実在したら、きっとこうに違いない」
と信じるに充分な迫力と細密度だった。
このイラストは、
↓劇場版(1977)のポスターに多用され、
ロマンアルバムのパーフェクトマニュアル2(1983)の表紙を飾り、
ヤマト現役期を終了。
1990年のLD「TVシリーズ PART1 パーフェクトコレクション」の
7枚全てのジャケットに使用。
その後は、2008年2月発売の、
↓DVD特典新1/700キットのボックスアートに使用されるも、
(※アメブロの表示規格が変更になり、どれだけ大判の画像を置いても、横600ピクセル表示になりましたとさ)
キットは必ずしも、イラストの立体化というわけではなかった。
それもそのはず、
このイラストは、一般的な透視図法では描かれておらず、
したがって実写画像や、
それに準ずるCG像とは合致しない。
じゃあ、どういう描き方なのかというと、
何百メートルもあるヤマトの巨艦に、
視界全体に入りきらないほど近づいて、
少しずつ立ち位置をずらし、そのたびに視点が変わって、
時に見上げ、時に見下ろしながら、
最終的に各部の画を強引につなげたもの。
この視点移動を、
別の方法で解説した人(前出のカエル課長)もいる。
というわけで、当該キットは、
●ブルワーク(艦首の波除け板)
●フェアリーダー(ブルワークに打ち抜かれた、丸い凹み)
●波動砲口
——の3点セットは、
↓まったくこのイラストには合致しない。
(上段左)DVD付属新1/700スケールキット。
(中段右)2010年末に発売された新1/500スケールキット。
↑(下段)2013年末発売の「2199」1/500スケールキット。
売り上げランキング: 68,581
売り上げランキング: 33,403
DVD版はともかく、
「2199」版の該当箇所は、
必要なものが失われる一方、
いらない余計なものが付け足されている感じで、
もはや改良ではなく改悪に過ぎず、
立体としての魅力をまったく感じないんだが…。
↓2014年1月25日に発売された、超合金魂は、
アニメ3DCGデータまんまという触れ込み。
売り上げランキング: 20,724
となると波動砲口周辺の、
各部をただテキトーにならしてつなげただけで、
機能無視のノッペリした造形は、
メーカー側(バンダイ)の責任ではなく、
アニメ作品(2199)そのものの問題なのかも。
なんにせよ、
“ぬえ”のイラストどおりの立体製品に、
お目にかかった例はなかった。
むかしからヤマトは、
画(絵=2D)としてのウソがあり、
そのままの立体(3D)化は不可能といわれたが、
“ぬえイラスト”の全体はムリにしても、
部分なら再現可能なはずでは?
そしたらついに、
立ち上がった人がいましたよ!
↓どーですか、お客さん!
やればできるじゃ、あーりませんか!
この作例は、
一部では、すでに知る人ぞ知る、
森雪の旦那氏が、
2015年5月21日と、
2015年6月4日に、
自身のブログで公表したもの。
ヤマトの基本的なアウトラインと有機的にからみつつ、
ブルワーク、フェアリーダー、砲口という、
機能ならではのデザインが引き立っているのもさることながら、
↓TV版アルカディア号のデザインと同様に、
この時期の宮武デザインが、
『 JAWS/ジョーズ』(1975)の影響をモロに受け、
売り上げランキング: 3,529
↓ガッツリとホオ(ホホ)ジロザメチックになっていたのが、改めて明らかになると共に、
↑ブラスタルゴ氏が透視図法で正確に描いた、「設定三面図に忠実なヤマト」にも、
相当に肉薄していることも判明。
そうなると、あれこれいじくり回した割には、
デザイン的にも機能的にも、ほとんど貢献しなかった、
「2199」のメカ再設定って、
↓公正を期すために、「2199」版とホホジロザメを並べれば、
↑さすがに同じ部分だから似てはいるけど、引かれているラインの無駄さや、立体としてのスキが目立つ。
売り上げランキング: 7,929
結局「大山鳴動してネズミ一匹」だったんじゃないの?
いやいや、この状況をもっと的確に表す諺(ことわざ)が、あるじゃないか!
森雪の旦那氏の作例こそ、「神は細部に宿る」
で、
「2199」版ヤマトこそ、「悪魔は細部に潜む」
ではないか。
と、オチがついたところで、今日の記事は、おしまい!
蒼きウルトラマンへの憧憬:ビクトリーナイト〈2〉/ウルトラマンは何人?〈19〉
これ(ビクトリーナイト〈その1〉/【補完】何人いるの、ウルトラマン?〈その18〉)の続き。
売り上げランキング: 9,160
ビクトリーからビクトリーナイトへのモデルチェンジで、
体のブラックの部分が、
ことごとくブルーやシルバーに置き換えられたのは、
↓黒いウルトラマンは悪いヤツに決まってるという、
↑たちの悪い先輩たちが築いてしまった風評を、
たかだか新米のビクトリーひとりでは、変えようもなかったから。
では、黒から置き換える色が、
どうしてブルーだったのか?
ビクトリーナイトは、
「ウルトラファイトビクトリー」で初登場、
ウルトラマンビクトリーの強化形態で、
↓ウルトラマンヒカリから与えられた
↑笛状の武器、ナイトティンバーの力で、
カラーリングが青を基調としたものに変化している。
売り上げランキング: 8,570
売り上げランキング: 3,783
——ってことになってるが、
こんなのは、
●先にブルーに変更することが決まってて、
●その由来として、青いウルトラマンのヒカリ(2006)が、強引にこじつけられた。
だけのこと。
青いウルトラマンの先例は、
ティガ(スカイタイプ・1996)、ダイナ(ミラクルタイプ・1997)、
↓ティガ(左)の体色は、厳密にはパープルブルー。
↑ダイナ(右)はミディアムブルー。
売り上げランキング: 58,193
売り上げランキング: 108,901
アグル(1998)、
↓ニセ・アグル(左)と戦う、ウルトラマンアグル初期形態(右)。
V2(バージョンツー)の登場で、今では初期形態のアグルを新作映像やライブステージで目にする機会は消滅している。
売り上げランキング: 90,018
売り上げランキング: 8,459
コスモスルナモード(左・2000)、
スペースコロナモード(右・2002)
売り上げランキング: 4,580
売り上げランキング: 192,565
レジェンド(2003)
レジェンドは、コスモス・フューチャーモードとジャスティス・クラッシャーモードの合体戦士。
売り上げランキング: 65,491
売り上げランキング: 98,393
売り上げランキング: 63,041
ネクサス(ジュネッスブルー・2004)
売り上げランキング: 61,439
等々、事欠かないのに、
↓ステージショーとはいえ、ヒカリ(左)、ダイナミラクル(中)、ネクサスジュネッスブルー(右)の体色のキーカラー(基本色)は、
3人とも、同じミディアムブルーだとわかる。
なんであえてヒカリなのか?
それは『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦!ウルトラ10勇士!!』で、
ギンガ、ギンガS、ビクトリーと関連づけが完了した8人、
①ティガ②ダイナ③ガイア④コスモス
⑤ネクサス⑥マックス⑦メビウス⑧ゼロ
——をふりかえらずに、新たに割り振れる青いウルトラマンが、
ヒカリしか残っていなかったから。
とはいえ、
↓ヒカリだって、メビウスの客演ウルトラマン、
条件はガイアの客演ウルトラマン、↑アグルと同じではないか。
アグルはしかし、ビクトリーをナイトに昇格させる役目を担うには、力不足。
アグルは地球の海の青い光の巨人=広義の地球人。
ビクトリーは有史以前、地底物質を巡って古代人の間で争いが起きた時に宇宙から飛来し、古代人の「選ばれし者」に自らへ変身する力を与え、戦いに終止符を打った。=あくまでも地球への来訪者であり、宇宙人。
だが、「太古の地球環境由来のウルトラマン」という設定が、かぶっている。
さらに↓アグル(右)には、ナイトティンバーなるハードウェアを供給する役目など担えない。
一方で↑ヒカリ(左)は、
以前は光の国の宇宙科学技術局に所属するエンジニアで、メカに精通。
↓肉体派のシルバー族(右)や、
↑レッド族(左)と比べ、頭脳派のインテリとされるブルー族。
さらに地球で初めてその姿を見せた時は、ハンターナイトツルギとして、
↑ヒカリ(右)が戦っているのは、ババルウ星人が変身したニセ・ツルギ。
アープギアという鎧(よろい)をまとっていたほどの、
バリバリのハイテク駆使タイプ。
売り上げランキング: 79,462
とまあ、一応説明はつくにせよ、
いざ本編を見ると
「なんでこいつが、ここにおんねん?」感が拭えない、
「ファイトビクトリー」へのヒカリの唐突な登場だった。
さすがに次回こそ、
どうしてビクトリーナイトの色をブルーにしたのかの、
ホントにホントの理由を明かします。
いつもどおり、気がついた人も、次回まではヒミツだよ。
AT-STモデルチェンジの真相(後編)/〜にまつわるエトセトラ〈その7〉
これ(AT-STモデルチェンジの真相(前編)/~にまつわるエトセトラ〈その6〉)の続き。
『ジェダイ』版のAT-STも、
当初は『帝国』版のスカウト・ウォーカーを、
そのまま劇中に出す予定だったのに、
どうして変更されたのか。
フルスケールのセットの図面(ブループリント)は、
『帝国』用のスタジオモデル(撮影用ミニチュア)と、
同じプロポーションで、
完成全高は320インチ、約8.13メートルのはずだった。
しかし実際に、この寸法(プロポーション/バランス)で、
セットを建造するのは無理があった。
横並びの小窓2つから、キャビンは2人乗りと設定され、
そうなると、頭部はかなり大きい割に、
それを支える脚部は、あまりにも細長く、
華奢(きゃしゃ)過ぎた。
このまま建造したら、絶対倒れる!
そこでジョンストンは、AT-STの再設計に着手、
安定して立てるように脚部を縮めて、
全高を20フィート6インチ、6.25メートルに変更した。
このデカ頭・短足の新生AT-STのデザインでミニチュアを作り直し、
スケッチのポーズ(直立脚フル伸展時)で全高40センチ、
しゃがみ気味のポーズで全高38センチとなった。
そう、AT-STの全高に幅があって一定しないのは、
姿勢によって高さが変わるからで、
これがスケール問題をややこしくしている。
さらに通常、
スタジオモデルはスケールを考慮して制作するが、
今回はこの限りではない。
というのも、
『帝国』版のミニチュアを基本に変更点を反映すれば、
完成モデルの大きさは、おのずと決まるが、
その際にスケールは、まったく考えられていないから。
これで外形は固まったものの、
6.25メートルという全高は、再検討を迫られる。
というのも、
↓どうやらケナー社のフィギュア用ビークルを参考にしたらしい、
↓スケッチのウォーカー頭部と人間との対比では、
↑シナリオで用意されている、
巨漢チューバッカがコクピットに収まるなんて、
とうていムリ。
そこで全高6.25メートルというのは廃案に。
↓40センチモデルは、ストップモーション用なので、
↓ポール・ヒューストンが、破壊用の大型モデルを制作。
↑コクピットには、1/9スケール、立像で20センチサイズのフィギュアがおさまり、
↓安定のしゃがみ気味で、全高86センチ、
おそらく当初の背伸び気味の直立で、全高90センチになる設計で、大型モデルが完成。
これが1/9スケールってことは、
90センチ×9=8.1メートル。
なんのことはない。頭部が大型化され、脚が短くなっただけで、
全高は当初のブループリントどおりの、
320インチ、8.13メートル(脚部フル伸展時)に戻っただけのこと。
これに伴い、
40センチサイズモデルは、約1/20スケールと確定。
では、フルスケールのセットは、
しゃがみ気味の大型1/9スケールモデル、
86×9=7.74メートルに
合致するのか?
↓こちらが人物との対比がわかる写真だが、
↑人物の身長がわからない。
英米人の平均、180センチでやるしかないが、
正面写真の人物は、ILMのデニス・ミューレンで、
↓彼はベイダーと肩を並べる長身である。
ベイダー役、デビッド・プラウズの身長にも諸説あるが、
ミューレンも186~188センチは確実にある。
そこでミューレンの上下をゆとりを持ってトリミング。
縦225ピクセルが、190センチ相当とする。
AT-STは、縦927ピクセルだから、
225:927=190:x
x=782.8
ということで、約7.8メートルと、ほぼ妥当な数値が導き出せる。
●姿勢の違い
●デニス・ミューレンの身長が非公表
——という諸条件の割には、
けっこうイイ線ついてるんじゃないか。
AT-STの全高、直立8.1メートル/しゃがみ7.8メートル説を裏付ける立体製品に、
2009年に発売された、
↓コード3(スリー)のダイカストがあって、
全高12インチ(30.48≒約30.5センチ)で、スケールは1/26と公表されている。
30.48×26=792.48
つまりこの姿勢で7.9メートルだから、正確。
一方で、
バンダイの1/48スケールプラモ、
AT-STの完成見本を模型店の店頭で見かけたら、
思ったよりでかくて、なんだか間延びしていてガッカリした。
バンダイの発表では、プラモの全高は182ミリ。
182×48=8.736メートル
8.7メートル?
それって、ブループリントの全高設定、
かつ、ジェダイ版がうんと背伸びした8.13メートルより、5メートル50センチ以上(下記コメント参照)デカイが、なんで?
1/45スケールでも、
182×45=8190。
約8.2メートルと、まだでかい。
どうやら、現在のAT-STの全高設定が、
8.6メートルだからってことなんだろうが、
6年前に正しい全高=実測値に基づいて、コード3が出てるのに、
今さら公式設定の原則論に戻っちゃうのは、
責任回避としか思えないが?
結局、バンダイのAT-STは、ほんとの1/48スケールじゃなくて、
それよりかなりデカイんだから、
他の同スケールのプラモデルと並べたって意味がないし、
さらにバンダイの1/48スケール表示のXウイングは、
本来のサイズよりも小さいので、
ますます揃わない。
2015年にもなってこの失態は、
バンダイに真の設計者が不在なことのあらわれといえる。
どうやらネットに豊富にある、スケール関連情報が、
英語で書かれてる時点で、
バンダイ製品には反映されない体制なんじゃ?
もっとハッキリ言うと、
バンダイには、英語と数学(算数)のできる社員がいないらしい。
また何年かして、
バンダイの権利が消失して、
別メーカーが、「今度こそ正確です」と高らかに宣言して、
たとえそれがホントでも、
「じゃあ買おう」より、「もういいよ」の方が多いのでは?
いや、他社でなく、バンダイがガンプラみたいに同アイテムを何度も出し直すかもしれないが、
それはそれで、「最初のはなんだったんだ?」ってことになる。
日本って、ほんとにダメな国になっちゃいましたね、しかし。
マックスのピグモン/GPV(16)/ふぞろい怪獣(23)
前回(ガラゴンとガラQ/ふぞろいの怪獣たち・22/ガラ&ピグ編・15)が、
2004年の「ウルトラQ dark fantasy」のガラQ、ガラゴンだったので、
今回はその翌年、
2005年の『ウルトラマンマックス』に登場したピグモン。
例によって、該当話は全く見てないので、
Wikiに頼り切ると、
第5話「出現、怪獣島!」、第6話「爆撃、5秒前!」、第36話「イジゲンセカイ」に登場。
別名:電脳珍獣
身長:1.5メートル
体重:95キログラム
設定では古代人に作られた人工知能とされており、怪獣島(サブジェクト・ファントム)を制御するためのシステムの一部である。
売り上げランキング: 211,688
先代のピグモンは登場した時点で石像であったが壊され、カイト隊員になついた個体が最後に石像となり、暴走する島を消滅させる。
売り上げランキング: 494,202
のちに第36話で再登場。シャマー星人の陰謀により新しいレッドキングともども再びこの世界へと出現。シャマー星人の攻撃を受け、エリーと同化した状態になる。エリーの姿のまま周囲(とくにミズキ隊員)が気をもむほどカイトになつくが、最後は、シャマー星人の特殊なエネルギーを使った銃によってマックス( = カイト)をかばい、ピグモンのみが異次元に飛ばされ、再びサブジェクト・ファントムへ戻る。
……。
何度読んでも、ちっとも頭に入って来ませんが?
造形的には、
↓ガラモンと混同されることなく、
↑ピグモンとしか認識されない線を狙ったようで、
↓その点ではたしかにうまく行ってはいるが、
あまりに平たい顔は、造形的には優れていると思えず。
↓「レッドマン」のガラモンの悪夢を想起させる。
それなのに、「マックス」を機に新造された、
このピグモンのスーツは、
ほかの「マックス」「メビウス」に再登場した怪獣の新調スーツ、
すなわち、
●エレキング
●レッドキング
●アントラー
●ゼットン
●ゼットン星人
●キングジョー
●ゴモラ
●メトロン星人
●ピット星人
●ダークバルタン
**************
●グドン
●バードン
●ミクラス
●サドラ
●ツインテール
●ウインダム
●ムカデンダー
●マグマ星人
●バルキー星人
●サラマンドラ
●ベムスター
●アーストロン
●ヤプール
●バキシム
●ドラゴリー
●ベロクロン
●ノーバ
●メイツ星人ビオ
●ゾアムルチ
●フェミゴン
●ババルウ星人
●ホー
●メビウスキラー
●メフィラス星人
●ルナチクス
——と同様に耐久性に優れていたため、
「マックス」以後も、
『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』(2009)
売り上げランキング: 60,719
K76星に住んでおり、ウルトラマンゼロを慕い彼の特訓を見守る。劇中、ゼロがウルトラマンレオを投げ飛ばした際に崩壊して来た岩塊に潰されそうになるが、ゼロに助けられる。
「めちゃイケ!」タイアップにも、ピグモンは登場。
↓この番組の様子は、こちらで。
↑『サーガ』(2012)タイアップの2012年4/2放送「ロンブー&チュートの芸能人ヒットソングで爆笑ショーバトル!」では、本編に出て来ないピグモンがPVに出演。
『大怪獣バトル ULTRA MONSTERS』(2007-2011)の、
雑誌『てれびくん』付属解説DVDには、
実写でウルトラマンマックスの時の着ぐるみが登場する。
『ウルトラゾーン』(2011)
第11、12話「スフラン島の秘蜜 (前編&後編)」に登場。
第9話アイキャッチでは、工事現場の作業員と並んでおり、
最終回の第23話では、通勤中のタカダ・リホ隊員の隣でうたた寝している姿と、夜に現場監督の隣にいる姿が描かれている。
第11話「怪獣漫才」では(ソフビ人形の)ナックル星人に、ガラモンがピグモンとそっくりと指摘される。
売り上げランキング: 253,231
『ウルトラゼロファイト』(2012-13)
第1部「新たなる力」で、バット星人グラシエが怪獣墓場から間違って蘇らせた怪獣。
「目障り」という理由で殺されそうになったところをウルトラマンゼロに助けられ、以後はゼロを見守り、応援する。最終的にはルナミラクルゼロによって救われ、戦いを終え怪獣墓場から旅立つゼロを見送る。
第2部「輝きのゼロ」では、ゼロをおびき出すエサとして捕らえられる。最終的にはウルティメイトフォースゼロとともにマイティベースで暮らすことになる。
売り上げランキング: 17,055
——と、円谷プロの映像作品に、
スーツのデビューから8年後まで、さんざん使い回されただけでなく、
近年のJR博多シティのCMでは、
2014年3月の「Amu Ultra Renewal」編の別バージョンで
ウルトラの母、バルタン星人、ダダと共に登場。
2014年6月のアミュ博多/アミュエスト/アミュ鹿児島「Amu Ultra Bargain」の別バージョンでは、
ウルトラの母、ダダ、ジャミラと共に登場。
2015年春の「Amu Est Ultra 1st Anniversary」編では、単独で出演。
2015年夏は、単独ポスターに続く、
「Amu Est Ultra Bargain」編では、カネゴンと共に登場。
現在(2015年夏)まで現役の、このピグモンで、
GPV(ガラモン・ピグモン・バリエーション)は打ち止めかというと、
どっこい把握する限り、あと2種類が存在している。
ので、また続く。
ギャラクティカ【後編】アンドルー・プロバート〈その2〉
デアゴスティーニ・ジャパン (2015-07-14)
デアゴスティーニ・ジャパン (2015-07-28)
これ(ギャラクティカ【前編】アンドルー・プロバート〈その1〉)
の後編。
「バトルスター・ギャラクティカ」(宇宙空母ギャラクティカ)
のサイロン兵士のヘルメットデザインで、
ジョー・ジョンストンとのコンペに勝った、
アンドルー・プロバートは、
そのまま兵士の全身、アーマーのデザインまで担当することになった。
プロバートはここでようやく、
サイロン兵士は、
あの爬虫類風エイリアンがアーマーを着込んでいるのではなく、
ロボットなのだと知った。
ここで紹介する一連の貴重な画像は、
全てこのページより。
↓「筋電に連動して発射するリストガン」という設定だが、ロボット兵士にこの原理は使えない。
↑左腕のリストアーマーのパネルは、凹・凸の2種類を検討。
プロバートの「ギャラクティカ」への参加は、
ともすればSWのデザインをなぞってしまう、ラルフ・マクォーリーや、
↓マクォーリーのサイロン兵の初期デザイン(左)は、SWのドロイド(RAシリーズ)と区別がつかない。
↑チンパンジーにスーツを着せて実現したロボット犬マフィットのデザインには、いつものジョンストンの冴えが見られない。
差別化のために、意図的にデザインのクオリティを下げた感のある、
ジョー・ジョンストンとは異なる新味を与えた。
メットの造形は実物大で行われたが、
↓最初期案は、ロボコップ風(1987)?
↑ボバ・フェット(1980)や、
↓クローン・トルーパー(2002)に近い時期もあった。
スリット内を、左右にユラユラと揺れる赤い眼光は、
「機動戦士ガンダム」(1979)のザク(ジオン軍モビルスーツ)のモノアイに影響を与えた。
全身の検討は、まずは人形で試され、
↓粘土原型の造形担当は、ラルフ・マッシー(Ralph Massey)
胸部は、メットのデザインの反復、
つまり、横幅一杯のスリットの下に、
シャッター/ブラインド状のスリット群が配置され、
このスリット群は、
↓サイロン兵が乗り込む、
↑サイロン・レイダーという戦闘機の機首のグリルにも通じる。
売り上げランキング: 109,822
↓金属光沢のあるメットとアーマーは、幅広のアルミテープをツギハギして完成。
↑長身の演者が扮した。
アンドルー・プロバートは、
ギャラクティカ艦本体の、バイパー戦闘機着艦口の設計も担当。
まずは構造図を描き起こし、
↑ミニチュアの該当部に貼り付ける、パース画も描いた。
↓実際の大きさは、こんなもの。
↑着艦口のだまし絵をのぞき込んで確認する、当時のILM主任、ジョン・ダイクストラ。
売り上げランキング: 73,731
売り上げランキング: 43,455
ここで、訂正記事。
プロバートが、マクォーリーのプロダクション・ペインティングに触発され、
直接本人と連絡を取ろうと思い立ったのは、
まだ『スター・ウォーズ』の公開(1977年5月25日)前。
雑誌各誌も、使用できる劇中スチルに事欠き、
宣材として映画会社フォックスから提供されたのが、
マクォーリーの絵ばかりだったし、
これにいち早く反応したのも、
プロバート自身が、アーティスト/デザイナーだったからこそ。
そしてプロバートが「ギャラクティカ」の制作に参加したのは、
1977年の夏。
「ギャラクティカ」用のジョンストンのデザイン画には、
08/02/77とある。
英米では月日の記述の順序が逆の場合もあるが、
SW公開前の2月8日に、「ギャラクティカ」の仕事はありえないので、
デザイン作業全般は、1977年夏だったことがわかる。
空前のヒットだったとはいえ、
映画公開から約2ヶ月後には、
ILMが次の企画に取り組んだのは、
ルーカスは、
ILM存続に気をもむ、責任者のダイクストラ以下のスタッフに、
外注の仕事を早急にあてがう必要に迫られていたから。
結局、「ギャラクティカ」でミソがつき、
ダイクストラとルーカスは袂(たもと)を分かつことになるが、
それがプロバートの次の仕事にも影響している。
——ここから先は、また次の記事で。
でもって、以下は今回のお題にからむ
おまけ。
「ギャラクティカ」も「バック・ロジャーズ」も、元を正せば「スター・ウォーズ」=ルーカスフィルムの財産という主張と証拠は、以前からある。
そのうちの一つ、「バック・ロジャーズ」のサンダーファイターは、
SWの最初期メカデザイナー、コリン・キャントウェルが、
最近公表した、当時の平面アートの中に、

戦闘機のディスプレイ案と思われるグラフィックがあり、
そこにはすでに、サンダーファイターが描き込まれていたりする!
(下右は、「ギャラクティカ」の資料に分類されている、マクォーリーのスケッチ群)
「ギャラクティカ」のオープニングにチラ見する(0:47あたり)、
平たい宇宙船は、アンドルー・プロバートがデザインしたものだが、
「スター・ウォーズ 反乱者たち」(2014)のゴーストに似ている。
もっとも、こんなマイナーな宇宙船ではなく、
『エイリアン』(1979)のナルキッソス(ナーシサス)あたりが元ネタだろうが。
そもそもプロバートだって、無意識のうちに、
フライングサブ(『原子力潜水艦シービュー号』1964-68)あたりに影響を受けてたのかも知れないしね。
青ざめたホントの理由:Vナイト〈3〉/ウルトラマンは何人?〈20〉
これ(蒼きウルトラマンへの憧憬:ビクトリーナイト〈2〉/ウルトラマンは何人?〈19〉)
の続き。
シルバーとレッドだけでは、
ウルトラマンのバリエーションはとうに尽き、
外形だけで新味を出すのは、もう限界。
そこでウルトラマンビクトリーは、
当初ギンガと対立する存在で、ワルの要素もあったことから、
正義のウルトラマンとしては禁断の、
ブラックに手を出してしまったが、
これはどうにもワルすぎた。
そこでビクトリーナイトでは、
もう1色、他の色を探ってみたら、
あとはブルーしか残っていなかった。
↓青いウルトラマンのブルーは一様ではなく、
ティガはパープル、ダイナはミディアムブルー、
アグルはミッドナイトブルー(紺)/インディゴ(藍)、
コスモスルナモードはロイヤルブルーなのに、スペースコロナはブルイッシュパープル、
レジェンドの青い部分はコバルトブルー。
ネクサスは大半がミディアムブルーで、一部コバルトブルー。
ヒカリは体側がミディアムブルーで、中央がミッドナイトブルー、
ルナミラクルゼロは、ダイナのミディアムブルーと、コスモスのロイヤルブルー。
※ただし画像からの判断で、正確という保証はありません。
という以外にも、
ビクトリーに黒をあしらい、
ナイトにブルーをあしらった理由はあって、
それは、
元ネタがライダーマン(1973)だから。
↓ライダーマン背景の架橋は、撮影2年前の1971年に運用開始されたばかりの、大泉の練馬インター近く…だよね?
売り上げランキング: 34,344
仮面ライダーV3(ブイスリー)は、風見志郎という単独主演が前半だったところに、
結城丈二(ゆうき・じょうじ)、ライダーマンという、サブヒーローが終盤で登場。
「ウルトラマンギンガ」の礼堂(らいどう)ヒカルは、
次回作「ギンガS」でも引き続き主演。
「S」からはサブヒーローとして、ショウという地底市民が共演する。
というわけで、
ビクトリーの額のV字は、
ライダーマンのマスクと、
ボディのブラックは、
スーツ(とりわけ下半身)から。
売り上げランキング: 62,617
ビクトリーナイトのブルーは、
ライダーマンのマスクの色に由来するというわけ。
「今さら気づいたの?
そんなの、ビクトリーの武器、
ウルトランスを見れば、
誰でも気づくじゃん!」
ウルトランスには、
EXレッドキングナックル、キングジョーランチャー、
サドラシザーズ、エレキングテイル、グドンウィップ等がある。
↑ウルフェス2014限定ウルトランスコンテスト最優秀賞の1つ、
バルタンセンジュカノン。
売り上げランキング: 7,411
——と、思われる方もいるでしょうが、
ライダーマンのカセットアームには、ロープアーム、パワーアーム、
スウィングアーム、ドリルアーム等がある。
売り上げランキング: 59,731
本ブログは勇み足で、
ビクトリーのウルトランスを知る前に、
とっくに元ネタを探っていたため、
ウルヴァリンじゃないかとか、
仮面ライダークウガじゃないかとか、
マジンガーZじゃないかとか、
迷走してるうちに、
ライダーマンとの関連づけの機会を、すっかり逸してしまった。
ビクトリーナイトとしてブルーに色替えしてくれたおかげで、
「はっ、そうだ!」
と思い出せたので、
結果的によかったんじゃないの?
ありがとう、ビクトリーナイト!
売り上げランキング: 2,209
熊井友理奈カミングアウト/よげんの書(21)/それまくる話(75)
タイトルの「熊井友理奈カミングアウト」ですが、
宇宙人は22年以上前に地球に来ていた!
=私はエイリアンとのハーフ
——ということではありません。
売り上げランキング: 15,620
7月29日放送の「ナカイの窓」
「デカイ人SP」で、
日本のダニエラ・ビアンキ(※当ブログで勝手に命名)こと、
熊井友理奈が、
長年の公称身長176センチを、
ついに訂正するイベントが行われた。
もちろん番組上は、
「ホントは公称の176センチよりあるんじゃないの?」
「実際に測ってみよう」
「あれ、181センチあるよ!」
「測るの久しぶりだったんで」
「これからは181センチを広言します」
——と言う流れだったが、
額面通りには受け取れず、
熊井友理奈がBerryz(ベリーズ)工房の事実上の終了後に、
売り上げランキング: 684
タレント活動休業同然の現状を打開するためには、
まずは疑惑のプロフィールを更新しない限り、
次のステップに進めないと悟ったのではないか。
そういや、以前に写真解析から、
熊井友理奈の身長は、181.96センチと算定され、
それが今回の「よげんの書」なんだが、
だったら0.96センチ=969.6ミリ(下記コメント参照)=1センチ弱の誤差は、
どこから生じたのか。
裸足の熊井友理奈の写真(画像)は、
↓今回の放送まで、見つからなかったからね。
↑それにしても、この背の高さで、
この細さ、華奢さは驚異的。
いや、そもそも「長身痩躯」(ちょうしんそうく)と言う言葉があることからもわかるように、
飛び抜けて背が高いことの条件は、
重力に引きずられずにスクスクと成長することだから、
デブの巨漢より、ヒョロヒョロ型の方が圧倒的に多いのはわかるけど、
大女(おおおんな)にありがちな、たくましさとかゴツさ、
↓青木愛(左・173センチ)とか、
↑南海キャンディーズのしずちゃん(右・182センチ)
みたいな、ガタイの良さとは無縁。
熊井さん本人の念願どおり、
スカイツリータレントになれたらいいですね!
もちろん元ネタは、
↓こちらです。
売り上げランキング: 34,231
ああ、そうそう。
このブログは、水・金・土・日の深夜、
日付的には、木・土・日・月の週4回の定期更新だが、
どうして水曜日放送の「ナカイの窓」関連記事を、
その水曜深夜に即座に行わず、
(まあ、さすがに記事が間に合わなかったにせよ)
その後も、金・土曜日の深夜もさけて、
あえて今日まで持ち越したかと言えば、
8月3日が熊井友理奈の誕生日で、
今日で22歳になるからなのだ!
売り上げランキング: 33,537
さて、「細い」つながりで、それまくる話をすると、
「ヒルナンデス!」2015年7月10日放送回の「3色ショッピング」で、
May J.と河北麻友子の、
メイジェイ「ひさしぶりだね。すっごいカワイイね、今日」
河北「細(ほっそ)いね、やっぱり!」
メイジェイ「何言ってるの!」
——という、褒め殺しのやりとりがあった。
そりゃまあ、May J.だって細いけど、
河北麻友子のガリガリ度は異常。
売り上げランキング: 2,685
こう言う心理を、「今夜くらべてみました」
2015年7月14日放送分、
「芸能界でイイ感じのポジションの女たち」
(実質上は『リアル鬼ごっこ』のプロモーション)で、篠田麻里子が、
「苦手な女性」として、「自分を卑下して、相手を褒める人」と告白。
「自分に自信のあるところを出すことで、反対に褒めてもらおうとしてるだけでは」
と分析していた。
幻冬舎 (2015-07-02)
売り上げランキング: 48,921
……。
なんの話だよ?
結局私が、ヒマをぶっこいて、テレビばっかり見てるのがバレただけ。
そんな2015年の夏。
売り上げランキング: 9,257
![ハンガー・ゲーム [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Aa8WPy7xL._SL160_.jpg)















![ヘアスプレー [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aJrHuHc3L._SL160_.jpg)
![ディパーテッド [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51fIKq4Xu0L._SL160_.jpg)
![マッドマックス2(初回生産限定スペシャル・パッケージ) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51SRWPEX-CL._SL160_.jpg)
![バットマン リターンズ [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51O5Tw5QuCL._SL160_.jpg)
![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版(31) 2015年 8/11 号 [雑誌]](http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/nav2/dp/no-image-no-ciu.gif)
![スター・トレックⅠ/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51I8mBlVqZL._SL160_.jpg)

















![ウルトラゼロファイト パーフェクトコレクション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51iSI5lQbPL._SL160_.jpg)
![劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦!ウルトラ10勇士!! [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/612TBbeSKNL._SL160_.jpg)



![スター・トレックⅥ 未知の世界/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2B9TIFo4jL._SL160_.jpg)







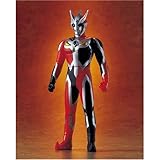










![宇宙空母ギャラクティカ コンプリート ブルーレイBOX [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51kW%2BXj-IVL._SL160_.jpg)











![AKB48 iPhone6ケース [渋谷凪咲] NEW水着 Ver.](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41p-FubT%2B4L._SL160_.jpg)

![竜神沼 オンデマンド版 [コミック]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41172VCF7KL._SL160_.jpg)







![ジョーズ [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xVd6dSoHL._SL160_.jpg)

















![大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE メモリアルボックス (初回限定生産) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Crv53%2BSFL._SL160_.jpg)
![ウルトラゾーン 全5巻セット [マーケットプレイス Blu-rayセット]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51HJF%2BIXM7L._SL160_.jpg)
![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版(31) 2015年 8/11 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MKKf2Os4L._SL160_.jpg)
![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版(32) 2015年 8/25 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sIZab0j-L._SL160_.jpg)









![未知との遭遇 製作30周年アニバーサリー アルティメット・エディション(2枚組) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51azsFB-JAL._SL160_.jpg)
![Berryz工房 ラストコンサート2015 Berryz工房行くべぇ~!(Completion Box) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AJT8ThX6L._SL160_.jpg)




